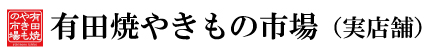 ネットショップと同じように、お店でも注文できます! |
||
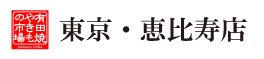 |
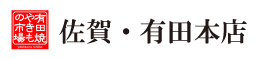 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 より大きな地図で 有田焼やきもの市場(有田本店) を表示 |
|
【営業時間】 |
【営業時間】 |
|
| >東京店の紹介はこちら | .>有田本店のご案内はこちら | |
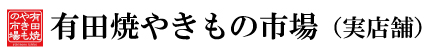 ネットショップと同じように、お店でも注文できます! |
||
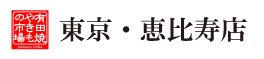 |
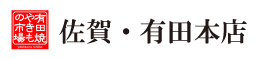 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 より大きな地図で 有田焼やきもの市場(有田本店) を表示 |
|
【営業時間】 |
【営業時間】 |
|
| >東京店の紹介はこちら | .>有田本店のご案内はこちら | |
琥山が作り出す金襴手の作品は、幾重もの工程を経て完成へと至ります。まず一般的な有田焼と同じ工程で素焼の品に絵付師がデザインを描き入れ、1300度の高温で窯焼成します。その後、金箔を重ねる空白部分を本漆で埋めていき、適度な乾燥状態になるまで数時間の間隔をとります。この本漆が陶磁器本体と金箔とを結びつける接着剤の役割を果たすのですが、湿り過ぎていても、乾燥しすぎていてもダメで、熟練の勘が頼りにされる作業です。
この金箔を適度に乾燥した漆の上に貼り付けていくのですが、これもやり直しが利かない一瞬の世界。非常に高い技術が必要です。
この技法こそが「金襴手」(きんらんて)と呼ばれる技法で、琥山だけがこの技法を今に伝えています。
澤田痴陶人(左)と琥山(先々代)(右)
1963年頃
一人のデザイナーの存在が、有田焼と金襴手の技法を結びつけました。京都の着物図案師で後に陶芸家として大成した「澤田痴陶人(さわだちとうじん)」がその人です。澤田痴陶人といえば、大英博物館で日本人初の個展を開催した芸術家として歴史に名を残している人物です。
痴陶人が縁あって有田の地(厳密には塩田町)を訪れた際、現・琥山の親族が直接指導を仰ぎ、試行錯誤の末、琥山独自の金襴手技法を確立させました。金箔を貼った後、窯焼成が必要なため、技術を確立するのに大変な苦労がありました。
現在でも製法の難易度は高いまま。決して他が真似できない独自の技術です。